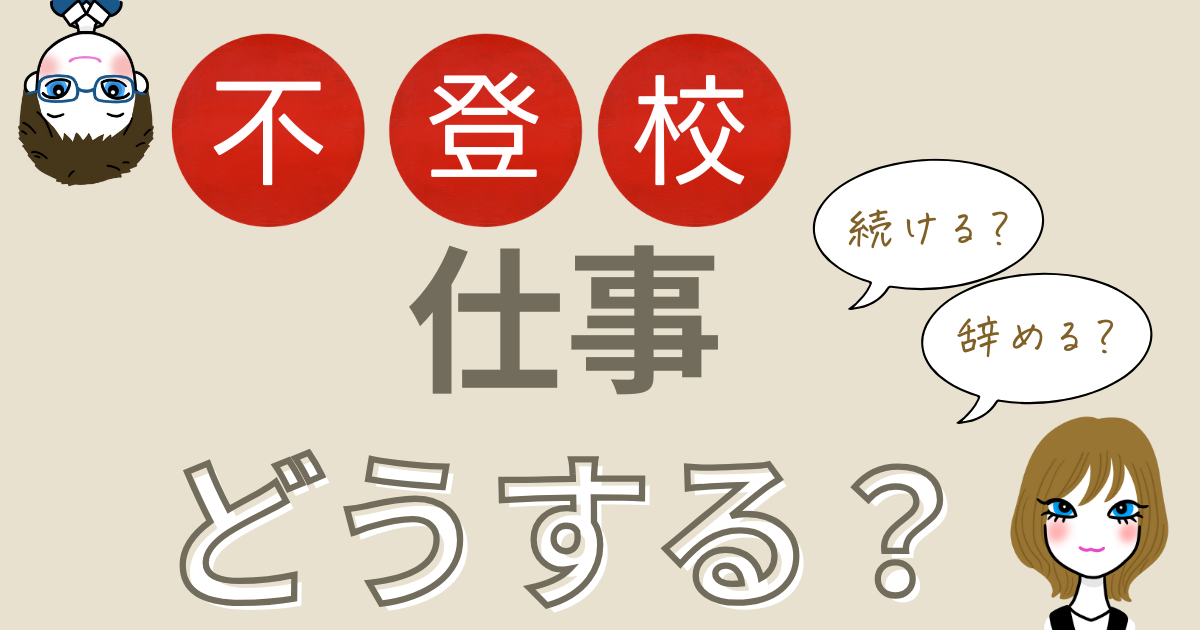子供が不登校になってしまって、毎日家で子供を一人で過ごさせるのが心配。
でもこれまで長く働いてきた仕事があって、できれば手放したくない。
仕事を辞めるのも不安だけど、続けられるかも心配です。
このような悩みを持つ方へ、不登校中学生の息子と2年向き合いながらフルタイムの仕事を続けてきた筆者が語ります。
✅本記事の内容
内容
この記事を読めば子供が不登校になったとき、母親がどんな働き方をすれば良いのか、子供の不登校に対応できる働き方と考え方がわかります。
※この記事は、日中一人で留守番できる子供が不登校になった場合を前提にしています。
子供を最優先にしたいけれど、乳幼児からの育児を乗り越えてママがこれまで続けてきた仕事を簡単に手放したくないですよね・・・!

私は仕事を続けて良かったと思っています。
実際に私が、不登校対応と仕事を両立させてきて思ったこと、
工夫したことやポイントをお伝えします。一緒に乗り越えましょう!
✅この記事の信頼性
・不登校の中学生息子と2年向き合った
・昼夜逆転の生活から、フリースクールに通えるように
・フルタイム会社員のため、平日夜と休日にコミュニケーションとっています
子供が不登校になっても仕事を続けて良い 3つのポイント

子どもが不登校になると、「このまま仕事を続けていいのだろうか」と悩むこともあるのではないでしょうか。
子どものそばにいた方がいいのか、収入やキャリアを守るべきなのか…。
ここでは「仕事を続けて、母も自分の人生を大事にしよう」という視点からお伝えします。
ポイント①:子供が元気なら、仕事を続けても大丈夫
子どもが不登校でも、母親が仕事を続けることは問題ありません。
母親がこれまで通りの仕事や生活をすることで家庭に安定感が生まれ、子どもに安心を与えられるからです。
ただし、子供がリストカットをするなど命に関わる危険があるときは、仕事に行くのは控えましょう
ポイント②:子どもを最優先にしながら働く
不登校の子供は、大好きなお母さんの働きかけが欲しいもの。
時間の使い方や働き方を工夫することで、子どもとの関わりの時間は減らさないよう意識しましょう。
在宅ワークや時短勤務など、働き方を見直して学校に行けない子どもと過ごす時間を確保しながら収入を得るのもありです。
ポイント③:「母の人生」を持つことが子どもにプラスになる
母親が自分の人生を持ち、仕事を続けることは子どもにとってプラスになります。
実際に「母がイキイキ働いている姿を見ることが励みになった」という不登校経験者の声もあります。
母親が自分の人生を大事にする姿勢は子どもに安心と希望を与えます。

私も自分で働いたお金で、美味しいものを食べたり、旅行に行ったり
好きなことをしてリフレッシュしていますよ
不登校の子どもを見守りながらできる働き方と体験談

「子どもを見守りたいけど、収入も必要…」そんなジレンマを抱えるお母さんは少なくありません。
不登校の子どもを支えながら取り組める仕事には、いくつかの選択肢があります。
ここでは具体例を挙げながら、両立しやすい働き方をご紹介します。
- 場所にしばられない在宅ワーク
- 専門性を活かした副業・フリーランス
- 柔軟にシフトを組めるパート・時短勤務
働き方①:場所にしばられない在宅ワーク
在宅ワークは子どものそばにいながら収入を得られる最有力な働き方です。
勤務先に在宅勤務があれば、まずは利用できるか、日数を増やせるか上司に相談してみましょう。
新しく仕事を探す場合は、これまで働いてきた業界+事務系職種などで
在宅勤務可能な勤務先を探してみましょう。
働き方②:専門スキルを活かした副業・フリーランス
これまでのキャリアやスキルを副業やフリーランスに活かす方法もあります。
自分の得意分野を生かせば、短時間でも高単価の仕事を受けたり、自分のペースで働くことも叶いやすいでしょう。
提供できるスキルがあるか、どんなスキルにニーズがあるか、まずは探してみましょう。
会社で培ったスキルが活かせるかもしれません。
働き方③:柔軟にシフトを組めるパート・時短勤務
外に出る仕事でも、シフトが柔軟なパートや時短勤務は両立可能です。
短時間で収入を得ながら、子どもの様子に合わせて勤務時間を調整できるからです。
スーパーや事務のパート、学童スタッフなどはシフト制が多く、子どもの予定や体調に合わせて働くことができるので
筆者の周囲でも多くいらっしゃいます。
体験談:筆者が子供を支えながら仕事を続けた方法
筆者自身は在宅勤務を活用しながら、週に3日ほど出社しながら仕事を続けてきました。
コロナの時に始まった在宅勤務制度でしたが、子供の不登校でもとても助かりました。
子供が不安定な状態の時は、日中に子どもの話を聞いたり一緒に食事をすることができました。
子供は「お母さんがそばにいる安心感」を得られ、私は「自分のキャリアを諦めずに済む」ことができました。

私は在宅勤務を活用して「子どもを最優先にしながら仕事を続ける」ことができて本当に良かったです
仕事も不登校の対応も両立させる3つのポイント

「子どもを優先したい、でも自分のキャリアも手放したくない」——そんな思いは決して欲張りではありません。
大切なのは、どちらかを諦めるのではなく、両方をバランスよく守る方法を探すことです。
筆者も意識してきた工夫や考え方をご紹介します。
- 宅配サービスや家事代行を利用し、無理なく働き続ける
- 子どもへの安心感はしっかり与える
- 将来を見据えて「自分のキャリアを育てる」
ポイント①:宅配サービスや家事代行を利用し、無理なく働き続ける
家事や仕事を完璧にこなそうとせず、力を抜けるところは抜くことが大切です。
完璧を目指すと母親が疲れ果て、結果的に子どもにも不安を与えてしまうからです。
宅配サービスや家事代行を活用して、「母親が元気でいること」が子どもの安心につながると多くの専門家が指摘しています。
ポイント②:子どもへの安心感はしっかり与える
働いていても「子どもが安心できる時間」を意識して確保することが重要です。
量よりも「質のある関わり」が子どもの心を支えます。
毎日必ず一緒に食事をする、夜寝る前にゆっくり話すなどの習慣を持つことで、子どもは「見てもらえている」という安心感を得られます。
ポイント③:将来を見据えて「自分のキャリアを育てる」
子どもの不登校期を、自分のキャリアを育てるチャンスと捉えることもできます。
今は制約があっても、将来に向けたスキルアップは必ず役立つからです。
オンライン講座や資格取得、副業などを在宅で進めて、数年後に正社員復帰や独立にチャレンジするのも良いでしょう。

私は「ITパスポート試験」を受けて、事務系の仕事を多めに担当させてもらって
両立しやすいようにしていましたよ
子供が不登校になっても仕事を続ける3つのメリット

子どもが不登校になると「自分の仕事をどうするか」で心が揺れ動くのは自然なことです。
しかし、母親が自分の人生を大切にしながら働き続けることは、子どもにとっても大きな安心につながります。
ここまでのポイントを改めて整理しておきましょう。
- 仕事を続けることは子どもにとってもプラスになる
- 金銭面が安定する
- 母が人生を楽しむことが子どもの希望になる
メリット①:仕事を続けることは子どもにとってもプラスになる
母親が仕事を続けることは、子どもの安定にも良い影響を与えます。
母親が精神的・経済的に安定していると、子どもは安心して日々を過ごせるからです。
心理学的にも「親の安定が子の安定に直結する」と言われ、働き続けることは子どもにとってマイナスではありません。

帰宅後は職場であったことや仕事のことを、子供にも話しています。
ずっと家にいる息子の視野が少しでも広げられたらいいなぁ
メリット②:金銭面が安定する
仕事を続けることで家庭の経済面が安定し、子どもの生活リズムや安心感につながります。
収入があると家計に余裕が生まれ、不登校の対応の中で発生する出費や教育費にも柔軟に対応できます。

我が家でも、母が働き続けた事で、民間のカウンセリングを受けたり、フリースクールに通ったり、趣味でピアノを習わせてあげることができました
メリット③:母が人生を楽しむことが子どもの希望になる
母親が自分らしく生きる姿を見せることは、子どもに希望を与えます。
母親が人生を楽しむ姿は「大人になっても自分らしく生きていい」というメッセージになるからです。

子供>夫>自分 が優先順位になっているお母さんが多いですね
中学生まで育てたのだから、母親ももっと自分の人生を楽しんでいいんですよ
【FAQ】よくある質問とその回答
子どもが不登校になってから職場での理解を得るにはどうすればいいですか?
不登校という言葉に抵抗を感じる人も多いため、状況を正直に伝えるより「家庭の事情で柔軟な勤務が必要」と説明すると理解を得やすいです。信頼できる上司に先に相談し、必要なら医師やカウンセラーの意見書を添えるとスムーズです。
不登校の子を支えるために仕事をやめるか迷っています。どう考えたらいいですか?
仕事をやめる選択肢は確かにありますが、再就職が難しくなるリスクも考慮が必要です。一度立ち止まり「支出見直し・支援制度・在宅ワーク」など複数の選択肢を並べて検討することで、後悔のない決断ができます。
子どもが昼夜逆転していて仕事に集中できません。どうしたらいいでしょうか?
生活リズムを無理に正そうとすると親子ともに疲れてしまいます。まずは「親の生活リズムは崩さない」ことを意識し、自分の睡眠や食事を整えることから始めましょう。親の安定が子どもへの安心感につながります。
子どもが「一人にして」と言う時、仕事に出てもいいのでしょうか?
一人になりたい気持ちは自立へのサインでもあります。その時間を尊重しつつ「困った時はいつでも呼んでね」と伝えておくと安心です。短時間の外出や仕事に出ることで、逆に子どもに自分の時間を持たせる機会にもなります。
子どもが家にいると気が散って仕事が進みません。どう工夫すればいいですか?
完全に集中できる環境を作ることは難しいですが、区切りの言葉や動作を決めると気持ちを切り替えやすくなります。「これから仕事を始めるね」と声をかけてイヤホンをつけるなど、子どもに合図を送る工夫が効果的です。
不登校の子どもが「お母さん働かないで」と言ってきます。どう返せばいいでしょう?
否定せずに気持ちを受け止めつつ「あなたのことを大切に思っているからこそ働いているんだよ」と伝えるのが良いです。親が働く意味を子どもなりに理解できると、安心して見守れるようになることも多いです。
周囲に不登校を話すと偏見がありそうで怖いです。誰に相談すればいいですか?
信頼できる親しい友人や専門の相談機関にまず話すのがおすすめです。匿名で相談できる窓口やオンラインコミュニティもあるので、無理に近所や親族に打ち明ける必要はありません。安心できる相手を選ぶことが大切です。
子どもの勉強が遅れているのに、私は働いていていいのでしょうか?
勉強の遅れに不安を感じるのは自然ですが、親が無理に教えようとすると衝突の原因になりやすいです。通信教材や家庭教師など外部の手を借りれば、母親は仕事と生活を安定させつつ子どもを支えられます。
母親が自分の時間を持つことに罪悪感を覚えます。どうすればいいですか?
自分の時間を持つことは決してわがままではありません。リフレッシュすることで心に余裕が生まれ、子どもにも穏やかに接することができます。罪悪感よりも「元気な母親でいるための必要な時間」と考えると気持ちが軽くなります。
まとめ

この記事のポイントをまとめます。
- 不登校の子どもがいても母親が仕事を続けることは悪いことではなく、家庭の安定と子どもの安心感につながります。
- 在宅ワークや専門スキルを活かした副業、柔軟なパート勤務など両立できる具体的な働き方は複数存在します。
- 「二兎を追う働き方」を意識し、子どもの安心と自分のキャリアの両方を守る姿勢が将来的な後悔を減らします。
- 家事代行や宅配サービス、カウンセリングなど利用できる制度を活用して子供と向き合う時間を作りましょう。
- 母が自分の人生を大切にする姿勢は子どもに希望を与え、「自分らしく生きていい」という安心感を育てる力になります。

仕事は、ライフステージや時代に合わせて変えていくもの
子供が不登校になったことでキャリアダウンした、と思わず
転職や副業も含めて、納得のできる働き方を見つけてくださいね
にほんブログ村